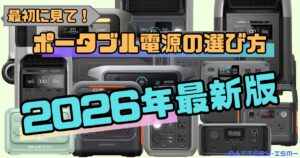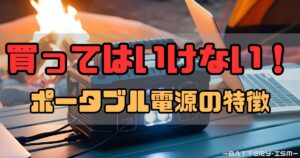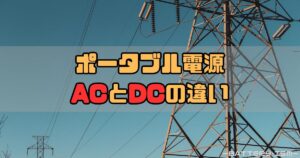ポータブル電源という言葉を聞いたり、家電量販店で実物を見たりする機会が増えたように感じます。
ポータブル電源市場は今まさに拡大途上にあるわけですが、ここに至るまでにどのような道のりを歩んできたのか私なりの考察を交えながら解説していきます。
ポータブル電源の誕生 (2016年~2018年)
世界で最初にポータブル電源を開発したのはJackery(ジャクリ)だと言われています。Jackeryは2012年にアメリカで創業しており、2016年にはポータブル電源を、2018年にはソーラーパネルを販売しています。今でも続くポータブル電源×ソーラーパネルの原型は2016年~2018年あたりにかけて誕生したわけです。
Jackery創業のビジョンは「グリーンエネルギーをあらゆる人に、あらゆる場所で提供する」であり、創業当初からポータブル電源は単なる大きなバッテリーではなく、誰でもいつでもどこでもエネルギーにアクセスできるというコンセプトのもと開発がなされていたことが想像できます。
一方日本ではすでに充電器やモバイルバッテリーを展開していたAnker(アンカー)がJackeryより先に日本にポータブル電源を投入します。それが2016年6月に発売されたPowerHouse(パワーハウス)というポータブル電源です。容量は434Whと小型で定格出力が120Wとなっており、最近のポータブル電源が容量300Wh以下でも定格出力が300W程度程度あることを考えるとこの時代はまだまだ控えめなスペックです。
Jackeryの日本参入とEcoflowの台等 (2018年~2020年)
Ankerに負けじとJackeryも2020年に日本市場に参戦し、Jackery 1000がAmazon、楽天市場、YahooショッピングといったECサイトのポータブル電源部門で売れ筋1位を獲得しています。同年にJackery公式オンラインストアもオープンし、オンラインを中心に勢力を拡大していきました。
さらにこの年にJackeryは日本の音響メーカーであるJVCケンウッドと業務提携しており、「JVC Powered by Jackery」名義でもポータブル電源を販売しています。当時無名だったJackeryがポータブル電源という日本で全く普及していなかった製品を売るためには、まずは認知を集め信頼感を持ってもらうことが重要なのでこのような戦略を取ったのでしょう。
そして同時期に遅れてあのメーカーが頭角を表し始めます。そうEcoflow(エコフロー)です。
今となってはAnker、Jackeryと並んで有名なEcoflowですが実は後発です。Ecoflowが創業したのが2017年で、その頃にはAnkerもJackeryもすでにポータブル電源を販売していました。そんなEcoflowが日本市場に入ってきたのが2019年末で、最初はクラウドファンディングでした。
このクラウドファンディングで最初に販売されたのがEFDELTAという機種で
- 業界トップクラスの1260Whの超大容量
- 最大出力1600Wで電子レンジやドライヤーも使える
- 0-80%の充電がわずか1時間という急速充電
といったこれまであったポータブル電源を凌駕するキャッチーなスペックで、実施期間約4ヶ月で当時の日本国内最高記録と言われる2億8000万円を調達しました。(現在もMakuakeで7位にランクイン)
EFDELTAの後にも立て続けにクラウドファンディングを実施しましたが、より小型のRIVER 600は5億1000万円(Makuake歴代2位)、さらに大型のDELTA Proは3億8000万円(Makuake歴代3位)を調達しており、この時期のEcoflowはまさに破竹の勢いだったと言えます。
三元系からリン酸鉄系への移行 (2020年~2022年)
2020年あたりもしくはそれ以前のポータブル電源には三元系のリチウムイオン電池が使用されてきましたが、徐々にリン酸鉄系のリチウムイオン電池を搭載したポータブル電源が現れ始めるのがこの時期です。
リン酸鉄系は三元系と比べてエネルギー密度が低く、ポータブル電源のサイズが大きくなりやすいというデメリットがある一方で、材料の構造が安定しているため熱暴走しにくく寿命も長いという圧倒的なメリットがあります。
リン酸鉄系のポータブル電源を最初に販売したのはBluetti(ブルーティ)というメーカーです。2020年5月に発売されたAC200Pは、サイクル寿命が3500回と記載されており、三元系のポータブル電源のサイクル寿命が500~1000回程度であることを考えると実に3倍以上も長く使える製品となっています。
2020年から2021年にかけて500Wh程度の小型から5000Wh超の大型までBluettiは立て続けにリン酸鉄系のポータブル電源を投入していくことになります。そしてBluettiに対抗するかのようにAnkerも2021年から2022年にかけてリン酸鉄系のポータブル電源Portable Power Stationシリーズのラインナップを拡充していく流れになりました。
さらに安全性を高める新リチウムイオン電池の登場 (2022年~)
リン酸鉄系ポータブル電源はポータブル電源市場の一つの転換点なのは間違いありません。より安全でより長寿命になったことで、一般ユーザーもポータブル電源に手を出しやすくなりました。
ですがリチウムイオン電池の進化はまだ止まりません。2022年にはDabbsson(ダブソン)というメーカーが半固体リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載したポータブル電源を、2023年にはYoshino(ヨシノ)というメーカーが固体三元系電池を搭載したポータブル電源を発売し話題になりました。
Dabbssonの半固体リン酸鉄系のポータブル電源は、リチウムイオン電池の中に入っている電解液という液体をゲルに置き換えたものです。液が漏れたり、吹き出した液に引火し炎が拡大するといったリスクが低減できます。
また、Yoshinoの固体三元系ポータブル電源は電解液もゲルも使っていないリチウムイオン電池です。(正極に一部液体材料を使用しているため全固体電池とは異なります。)そのため液漏れ、吹き出しのリスクもないですし基本的には燃えませんが価格が高いといったデメリットもあります。
今はリン酸鉄系のポータブル電源が主流ですが、今後は半固体リン酸鉄系や固体三元系も増えてくるのではないかと思います。そして最終的には全固体電池が搭載されたポータブル電源が出てくることでしょう。
AnkerのSolixシリーズが大ヒット (2023年)
2023年に入るとBluettiとAnkerの後を追って、EcoflowとJackeryもリン酸鉄系のポータブル電源を投入し始めます。春先にはEcoflowからRIVER 2 ProとDELTA 2 Maxが発売され、夏にはJackeryから2000 Plusと1000 Plusが発売されています。
そんな中、2023年秋にAnkerからPortable Power Stationシリーズの系譜を受け継ぎつつ、新たに確立されたブランドSolixシリーズが発売されます。Portable Power Stationシリーズと同様のリン酸鉄系のポータブル電源であり長寿命、加えて充電速度や出力などが向上しています。特に1000WhクラスのSolix C1000 Portable Power Stationは1000Whクラスのポータブル電源の完成形とも言える製品で、おそらく日本で一番売れたポータブル電源だと思います。
ポータブル電源大参入時代 (2024年~)
2024年に入るとポータブル電源は一定の知名度を獲得したためか、専業メーカー以外からも続々とポータブル電源市場に参入してきます。
- Aviot(アビオット):イヤホンメーカー
- Elecom(エレコム):デジタル機器メーカー
- DJI(ディージェーアイ):ドローンメーカー
- アイリスオーヤマ:家電メーカー
とはいえポータブル電源市場はこの時点でかなりレッドオーシャンになっているため、これらのメーカーはなんとか勝ち筋を見出そうとしています。例えばAviotは日本の会社であるという点を最大限押し出していたり、DJIは自社のドローン製品を充電するのに最適な専用ポートを搭載していたりします。
JackeryとEcoflowの反撃 (2024年)
2024年はAnkerの独走と新規参入メーカーに入り込まれないようにJackeryとEcoflowの反撃が始まった年でもあります。Jackeryからは基本モデルとなるNewシリーズ、EcoflowからはDELTA 3とRIVER 3が発売されました。これらのポータブル電源には両メーカーの対Anker戦略がよく表れており面白いです。
まずJackeryのNewシリーズの特徴がコンパクトさと軽さです。同じ1000Whクラスで比較すると以下の通りです。
| 製品 | サイズ/重さ |
|---|---|
Anker Solix C1000 Portable Power Station | 38cm×21cm×27cm/12.9kg |
Jackery 1000 New | 33cm×22cm×25cm/10.8kg |
Ecoflow DELTA 3 | 40cm×20cm×28cm/12.5kg |
JackeryのNewシリーズはセルトゥボディという構造を取っており、電池とポータブル電源のボディが直接統合されているためエネルギー効率が大幅に向上しており本体がコンパクトになっています。
続いてEcoflowはAnkerに対してサイズではなく性能で真っ向勝負を仕掛けています。
| 製品 | サイクル | 充電時間 | UPS |
|---|---|---|---|
Anker Solix C1000 Portable Power Station | 3000回(80%) | 58分 | <20ミリ秒 |
Jackery 1000 New | 4000回(70%) | 60分 | <20ミリ秒 |
Ecoflow DELTA 3 | 4000回(80%) | 56分 | <10ミリ秒 |
2024年時点では、知名度のAnker、軽量コンパクトのJackery、性能のEcoflowのような構図になっています。
価格低下と小型化の傾向 (2025年~)
2025年に入ってもJackeryとEcoflowは引き続き上記の路線で容量ラインナップの拡充を進めています。そしてBluettiからも日本専用モデルAORAが発売されたり、Dabbssonからも得意の半固体リン酸鉄ポータブル電源の新ラインナップが5機種も立て続けに発表されたりとまだまだ盛り上がっているポータブル電源市場です。
また真打のAnkerもSolix C1000の後継機種となるSolix C1000 Gen2 Portable Power Stationと2000WhクラスのSolix C2000 Gen2 Portable Power Stationを発売し対抗しています。
様々なポータブル電源が発売された2025年ですが価格低下と小型化の傾向があるように感じます。
まず価格低下ですが、例えばAnkerのSolix C1000は定価が139,900円だったのに対しSolix C1000 Gen2は99,900円と4万円も安くなっています。さらにEcoflowのDELTA 2 Maxは254,100円だったのに対し、2025年に発売された後継機種DELTA 3 Maxは209,980円となっており、こちらも4万円程度値下がりしています。世の中何でも値段が上がっているのにポータブル電源はむしろ下がってきています。
これには材料となるリチウムの値段が一時期と比べるとかなり落ちてきて安定してきたことや、ポータブル電源も色んなメーカーが乱立して価格競争に突入してきたからだと思います。どんな理由であれ消費者にとっては価格が下がっているのはありがたい話です。
続いて小型化ですがこれは容量が小さくてサイズも小さいポータブル電源が流行ってきたというわけではなく、2025年の新製品を見るとポート数を多少削ってもポータブル電源のサイズを小さく・軽くする傾向があるということです。例えば、DELTA 3 MaxはDELTA 2 Maxと同じ容量ですがポート数が5個も減り、その分3kg程度軽くなっています。
これはユーザーがより軽くて小さくて扱いやすいポータブル電源を求めているために、ポータブル電源が最適化されていっているのだと思います。結果的にはJackeryの方向性が合っていそうという感じなんでしょうね。なのでここからはJackeryはコンパクトなまま性能アップ、AnkerとEcoflowはハイスペックのままコンパクトにするような方向に進むと思います。
まとめ

この記事ではポータブル電源の歴史を解説しました。歴史といってもポータブル電源は誕生してからまだ10年も経っていない分野なのでまだまだこれからです。
- ポータブル電源の誕生 (2016年~2018年)
- Jackeryの日本参入とEcoflowの台等 (2018年~2020年)
- 三元系からリン酸鉄系への移行 (2020年~2022年)
- さらに安全性を高める新リチウムイオン電池の登場 (2022年~)
- AnkerのSolixシリーズが大ヒット (2023年)
- ポータブル電源大参入時代 (2024年~)
- JackeryとEcoflowの反撃 (2024年)
- 価格低下と小型化の傾向 (2025年~)
最後まで読んでいただきありがとうございました!